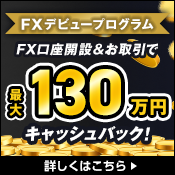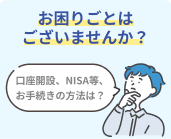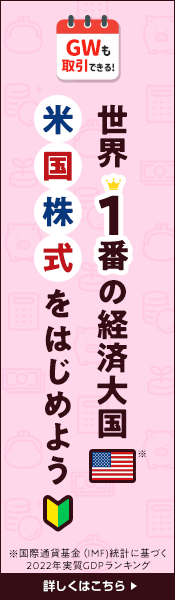音楽CDの販売が低迷する一方で、「音楽ストリーミング」の市場が急拡大しています。同分野の専業で世界最大手でもあるスポティファイが4月初旬に新規上場の予定で、市場の注目も高まっています。今回は音楽ストリーミング市場、その主要サービス、最大手スポティファイの事業についてレポートいたします。
図表1:当レポートで言及した主な銘柄
| 銘柄 | 株価(3/13) | 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|---|---|
| スポティファイ(SPOT) | - | - | - |
| アップル(AAPL) | 179.97ドル | 183.50ドル | 138.62ドル |
| アルファベット(GOOGL) | 1139.91ドル | 1198.00ドル | 824.30ドル |
| アマゾンドットコム(AMZN) | 1588.18ドル | 1617.54ドル | 833.50ドル |
| テンセント(騰訊)(00700) | 462.80HKドル | 476.60HKドル | 213.00HKドル |
- 注:スポティファイ(SPOT)は4月上旬にNY市場に上場予定です。
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
|
|
「音楽ストリーミング」が牽引する世界の音楽売上 |
今回は世界の音楽産業を牽引している「音楽ストリーミング」についてレポートいたします。音楽ストリーミングの世界最大手であるスポティファイがニューヨーク市場に上場予定で、同市場に対する関心が高まっているようです。
〇デジタル配信の増加で世界の音楽売上は底入れ
世界の音楽業界の売上は長期的に低落傾向が続いていましたが、インターネット経由のデジタル配信の増加がパッケージ(CD、DVDなど)の減少をカバーして、15年、16年と増加に転じています(図表2)。
16年は、パッケージが前年比8%減に対してデジタル配信は同18%増で、全体では同6%増でした。デジタル配信が初めて全体の50%を超えています。
デジタル配信は、さらに「ストリーミング」と「ダウンロード」に分けられますが、現在の拡大を牽引しているのは「ストリーミング」です(図表3)。16年には「ストリーミング」が前年比60%増えてデジタル配信の59%を占めた一方、「ダウンロード」は同21%減でした。
〇「ダウンロード」と「ストリーミング」の違い
「ダウンロード」と「ストリーミング」の決定的な違いは、利用者が音楽データを、前者では所有でき、後者では所有できない点です。
「ダウンロード」して所有する場合は、スマホやPCに保存したデータを再生して、いつまでも聴くことができます。ただ、聴けるのは1曲当たり200〜300円なりで個別に支払ってダウンロードした曲だけです。
一方、「ストリーミング」の場合は、データを所有できないため、サービスを解約すると聴くことができません。しかし、サービスに加入している間は、定額で数千万曲のライブラリーから自由に聴くことができます。
例えばアップルが提供しているサービスでは、「iTunes Store」が「ダウンロード」、「Apple Music」が「ストリーミング」になります。
音楽市場は長らく構造不況業種と見られていたと思われますが、これからは違うかもしれません。特にストリーミングは成長分野として注目できるでしょう。
世界売上が10億ドルを超えてからまだ5年で揺籃期にあると考えられ、従来とはビジネスモデルが異なるため、まだまだ市場の限界が見えていないところが楽しみな点です。
図表2:世界の音楽産業売上の推移
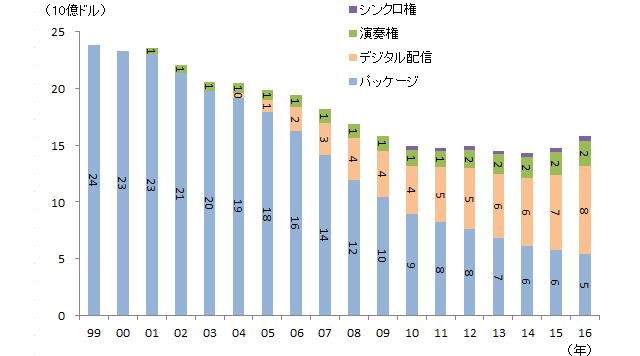
- 注:シンクロ権は、映画やゲームのような、音楽作品そのもの以外で楽曲を使う際の権利料です。
- ※IFPI(国際レコード連盟)のデータをもとにSBI証券が作成
図表3:急成長を遂げる「音楽ストリーミング」
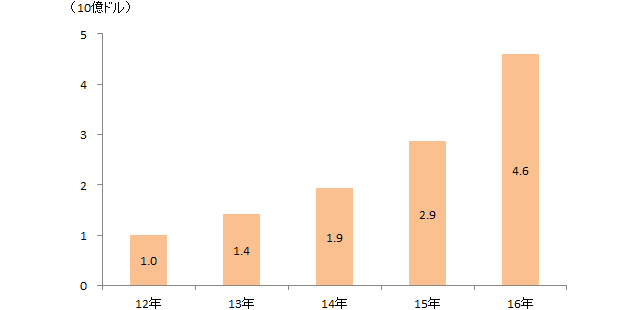
- ※IFPI(国際レコード連盟)のデータをもとにSBI証券が作成
|
|
「音楽ストリーミング」の主要サービス |
市場が急拡大している「ストリーミング」の主要なサービスとしては、スポティファイ(SPOT)の「Spotify」、アップル(AAPL)の「Apple Music」、アルファベット(GOOGL)の「Google Play Music」、アマゾンドットコム(AMZN)の「Amazon music unlimited」「Amazon prime music」などがあります。
「Apple Music」、「Google Play Music」、「Amazon music unlimited」は、いずれもインターネットのプラットフォーマー(※)が提供するサービスですが、奇しくも、個人が月額980円、ファミリーで月額1,480円と、ほぼ同一の利用条件です。彼らにとっては、様々あるビジネスのうちの一つに過ぎず、ここでガリガリ競争する必要はないということでしょうか。
※プラットフォーマー:他社がビジネスを行う基盤として利用できるサービス、システムなどを運営する企業。
一方、業界のリーダーながらプラットフォーマーではないスポティファイは、サービス中に広告が入るフリーのプランと月額980円の有料プランを提供しています。
プラットフォーマーの場合は企業に信用があり、既に何らかのサービスを利用しているケースが多いため、最初から有料サービスでも抵抗はないと考えられます。しかし、スポティファイの場合は、初めてのサービスとなるため、最初から有料プランというのは抵抗があるのでしょう。
フリープランで様子を見て問題なければ有料プランに移行するというプロセスが必要なようです。このサービス展開は成功していて、同社がストリーミング市場の拡大を牽引しています。
また、楽曲数は100万曲と少ないものの、Amazonプライムの会員であれば追加料金なく利用できる「Amazon prime music」も選択肢です。ライブラリーが好みに合っていれば、これで十分という消費者もいるでしょう。
これらグローバル展開しているメジャーサービスのほかにも、フランスの「Deezer」、韓国の「MelON」、米パンドラメディア(P)による「Pandora」、中国のテンセント(騰訊)(00700)による「QQ Music」などのサービスがあります。
また、主に日本でサービスを提供しているものでは、サーバーエージェントとエイベックス・デジタルの共同出資による「AWA Music」、LINE(LN)による「LINE MUSIC」などがあります。
図表4:音楽ストリーミングサービスの比較
| サービス | 楽曲数 | プラン |
|---|---|---|
| Spotify | 4,000万曲以上 | ・フリー 0円(広告あり、機能の制限あり) ・プレミアム 月額980円 |
| Apple Music | 4,500万曲 | ・個人 月額980円 ・ファミリー 月額1,480円 |
| Google Play Music | 4,000万曲以上 | ・個人 月額980円 ・ファミリー 1,480円(6人まで) |
| Amazon music unlimited | 4,000万曲以上 | ・個人 980円(プライム会員は780円) ・ファミリー 月額1,480円(6人まで) |
| Amazon prime music | 100万曲以上 | ・Amazonプライム会員の特典 (追加料金はかからない) |
- 注:2018年3月12日(月)時点です。
- ※各社WEBサイトをもとにSBI証券が作成
|
|
最大手スポティファイの事業概要 |
音楽ストリーミングの分野で世界最大手で、業界の売上拡大を牽引しているスポティファイをご紹介いたします。
同社は2/28(水)にSEC(米国証券取引委員会)に上場目論見書を提出、4/2(月)の週にニューヨーク証券取引所に上場見込みで、時価総額は200億ドル以上との観測です。
「インターネット」のカテゴリー別の「グローバルトップ」のため成長期待が高く、注目の新規上場案件となっているようです。また、新株発行による資金調達を行わない、「ダイレクト・リスティング」を行うことでも市場の注目を集めています。
〇会社概要
2006年に創業したスウェーデン企業です。2008年にサービスを開始してヨーロッパで成功、2011年に米国に進出、現在61ヵ国でサービスを展開(日本では16年9月から)しています。17年末の月間アクティブユーザー(MAU)は159百万人で、地域別構成は、欧州が37%、北米が32%、南米が21%、その他が10%となっています。
〇市場ポジション
グローバルシェアは、売上ベースで16年に42%でした。有料のプレミアムプランのユーザーは71百万人(上記のMAUに含まれる)で、業界2位の「Apple Music」に対して2倍近い差がついていると推定され、圧倒的なトップと言えるでしょう。
17年にはMAUが前年比29%増、プレミアムプランのユーザー数が同46%増と順調に増加しています(図表6)。事業展開している国での同社サービスの利用率(同社ユーザー数÷支払機能のあるスマホ台数)は13%で、今後の浸透余地が大きいとしています。
また、17年12月に中国の大手インターネット企業テンセントと、テンセントが設立した音楽ストリーミング子会社を含めて、株式を持ち合う取引を行っています。中国市場に進出する足掛かりとして注目できるでしょう。
〇事業モデル
世界3大レコードレーベルであるソニー・ミュージックエンタテイメント、ワーナー・ミュージック・グループ、ユニバーサルミュージックおよび独立レーベルの権利関係をまとめて扱うMerlinなどと楽曲配信のライセンス契約を結び、3,500万曲以上(目論見書ではWEBサイトの「4,000万曲以上」でなく、こうなっています)の楽曲へのアクセスを確保しています。
「音楽ストリーミング」のサービスを提供して、主に月額会費からなる収入を得ます。17年売上のうち、90%が会費、広告が10%です。同社の売上原価の多くは、アーティストに支払うロイヤリティからなります。17年12月期は売上が4,090百万ユーロに対して売上原価は3,241百万ユーロを支払っています。
同社は創業以来、80億ユーロ(約1兆円)を超えるロイヤリティをアーティストや音楽業界に支払っており、クリエーターと消費者が出会える場を提供し、双方にメリットのあるビジネスを目指すとしています。
業績は営業赤字が続いていますが、粗利率は15年12%、16年14%、17年21%と売上の拡大とともに上昇しています。売上と粗利益が順調に増加傾向にあれば、いずれ販売管理費をカバーして営業黒字化すると期待できるでしょう(図表5)。
同社の営業キャッシュフローは16年にプラスに転じて、17年は179百万ユーロのプラスでした。システム関係の大きな投資が無ければキャッシュは積み上がる事業構造で、新規上場に際して資金調達をしないのは、このためと見られます。
〇同社サービスを利用してみました
「Spotify」のフリープランを利用してみましたので、それをご報告いたします。
検索でアーティストを選ぶと、登録されている曲がストリームされます。ただ、その順序はランダムです。自分が聴きたい曲があっても、スキップ回数が制限されているため、自由に移動することはできません。
もちろん、広告も挟まれます。それでも、BGM的に流しておく分には、これでも十分でしょう。しかし、明確に聴きたい曲がある場合にはストレスになることがあるかもしれません。
月額980円のプレミアムサービスに移行すると、制限なくスキップでき、自分が聴きたい順番に聴けるほか、様々な機能が使えるようです。音質も良くなるそうです。
ライブラリーについては、筆者が興味のある70年代、80年代の洋楽は、問題なく何でもありそうでした。最近のアーティストでも、検索してみた限りではすべて登録がありました。
一方、邦楽については超有名アーティストは入っていません。例えば、サザンオールスターズ、嵐、スマップ、古いところでは大瀧詠一もありません。人気が高いコンテンツで、CDが売れる可能性があるものについては、ストリーミングに提供すると売上が減るとの判断があるのでしょう。
海外に比べて日本の音楽界は「Spotify」に限らずストリーミングに否定的と言われています。ですから、日本の状況だけを見て判断すると、間違ってしまう可能性があることには注意が必要でしょう。
図表5:スポティファイの業績推移
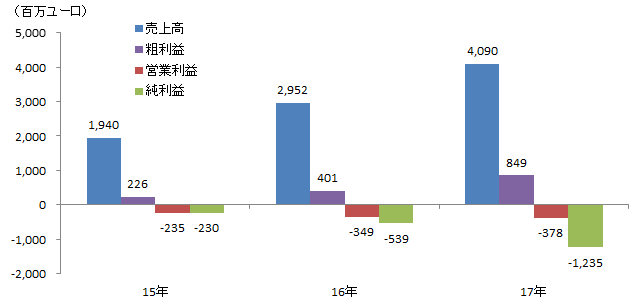
- ※会社資料をもとにSBI証券が作成
図表6:主要な営業指標
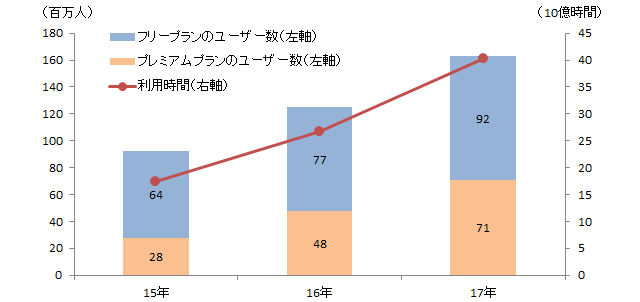
- ※会社資料をもとにSBI証券が作成
- ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。