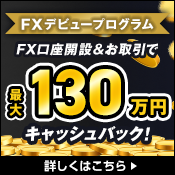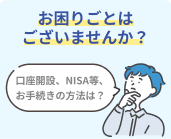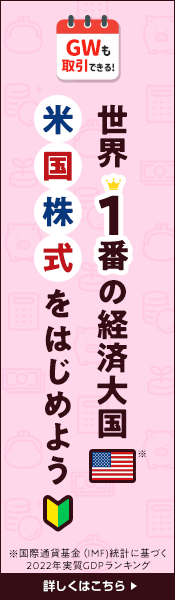約20年ぶりの円安が注目を集めるなか、比較的堅調だった人民元が急落し、海外投資家の警戒を誘いました。市場の一部では「2015年の人民元ショックの再来?!」と警戒する声も出ました。今回は、人民元安の背景と中国当局の動きを確認し、過去の経験則から株式市場への影響を考察してみたいと思います。
図表1 主な言及銘柄
| 銘柄 | 株価(4/26) | 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|---|---|
| iS MSCIチャイナ(02801) | 20.24香港ドル | 35.84香港ドル | 18.36香港ドル |
| ハンセンH株指数(02828) | 68.30香港ドル | 112.90香港ドル | 61.32香港ドル |
| Tracker Fund香港(02800) | 20.14香港ドル | 29.82香港ドル | 18.44香港ドル |
| iS FTSE A50(02823) | 14.70香港ドル | 21.60香港ドル | 14.54香港ドル |
| iS CSI300(02846) | 29.44香港ドル | 43.00香港ドル | 31.30香港ドル |
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
世界主要為替の年初来推移を確認してみると(図表2)、ロシアがウクライナに侵攻してから、ドル高/ユーロ安・円安が進みました。有事のドル買いやウクライナ危機の欧州経済への影響、米長期金利の上昇による日米金利差の拡大などが背景として指摘されています。
図表2 主要為替の対ドルレート逆数とドル指数の推移(2021年12月31日を100として指数化)
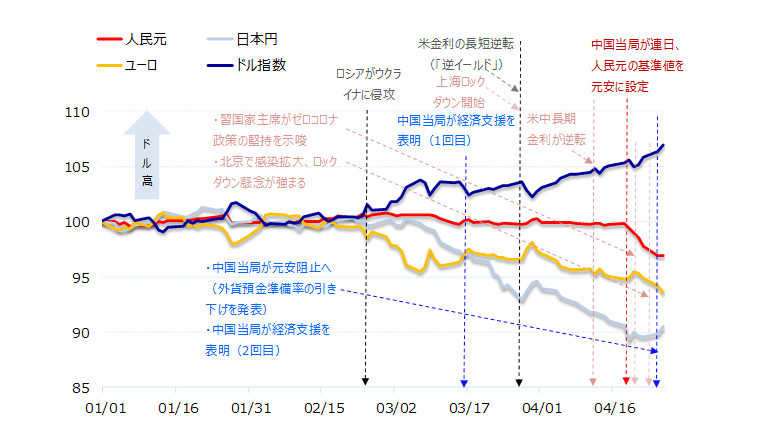
※Bloombergデータおよび各種報道をもとにSBI証券が作成
一方、人民元は4月半ばまで底堅く推移しました。中国が膨大な貿易黒字(2021年の貿易黒字は過去最高)を抱えていることに加え、中国人民銀行が人民元取引の基準値(中間値、以下「人民元の基準値」)を前日と同水準に設定し続けたことが背景にあります。
図表3 米中10年国債の金利差と人民元対ドルレートの推移(年初来)
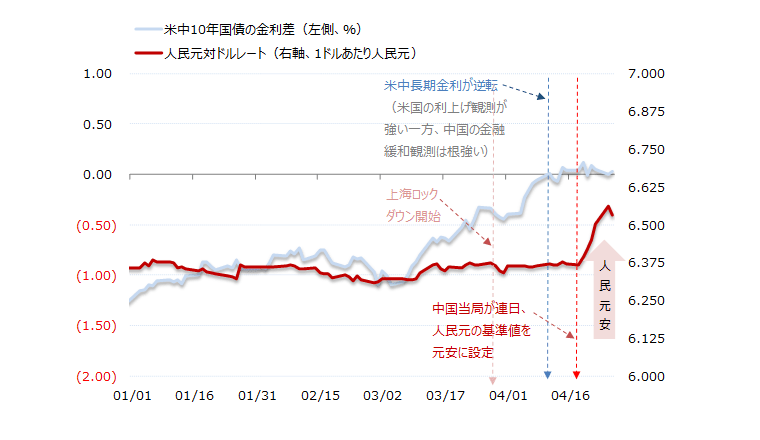
※Bloombergデータおよび各種報道をもとにSBI証券が作成
しかし、4/20に人民元は対ドルで急落しました。きっかけは、中国人民銀行が人民元取引の基準値を元安に設定したからです。実際、米中長期金利の格差縮小(マイナスからゼロへ)や上海ロックダウンによる経済への影響が懸念されるなか、為替市場ではある程度元安圧力が高まっていました。中国人民銀行の元安設定はこのような圧力によるものかどうかは不明です。一部では中国当局が景気減速への対応(輸出促進)措置として元安を容認した可能性もあると指摘されています。
その後、中国人民銀行は連続5日で人民元の基準値を元安に設定しました。それを受け、為替の投機筋からは「中国当局は元安を容認する姿勢だ」との声が上がりました。一部では「2015年の人民元ショックの再来?!」と警戒する声も出ました。軟調地合い(*)も相まって、人民元ショックの再来を警戒し、株式市場では中国株売りの動きが強まりました。(*中国人民銀行が大方の予想に反して4月中旬に利下げを見送ったことで中国株市場は軟調な地合いが続いていました。)
図表4 人民元対ドルレートと人民元の基準値の対前年比の推移(2015年以降)
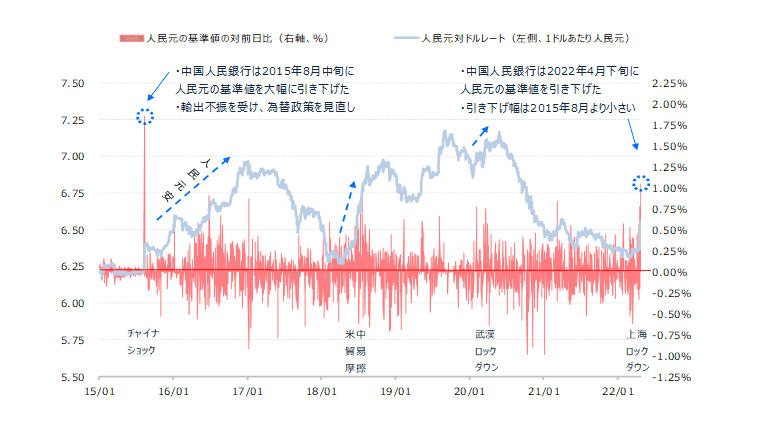
※Bloombergデータおよび各種報道をもとにSBI証券が作成
元安・中国株安が止まらないなか、中国人民銀行は4/25の夜に外貨の預金準備率を1%引き下げると発表しました。外貨の流動性供給につながるため、元売り・外貨買いの動きを弱める効果があるとされています。ただし、今回の引き下げは直接的な効果よりも中国人民銀行の「意志表明」として捉える向きが強いです。つまり、中国人民銀行は「ある程度の元安は容認するが、人民元の急落は望んでいない。元急落なら介入する用意がある」と市場にメッセージを送り、いわば「人民元ショックの再来」懸念の払拭に動きました。
それを受け、4/26の香港市場では、人民元対ドルレートおよびハンセン指数とハンセンテック指数がともに反発しました。ただし、株価指数の上昇率はハンセン指数(前日比0.3%上昇)よりもハンセンテック(同2.9%上昇)が高いです。背景には、中国人民銀行が4/26に、実体経済への支援強化と同時に、ネット大手に対する締め付けの「早期終了」に言及したからです。具体的には、「主要インターネット企業に関する是正作業をできるだけ早期に完了させ、プラットフォーム経済の健全な成長を促す」方針が示されました。なお、中国当局がネット大手に対する締め付けの「早期終了」に言及したのは、これで2回目となります。
図表5 ハンセン指数とハンセンテック指数の推移(年初来)
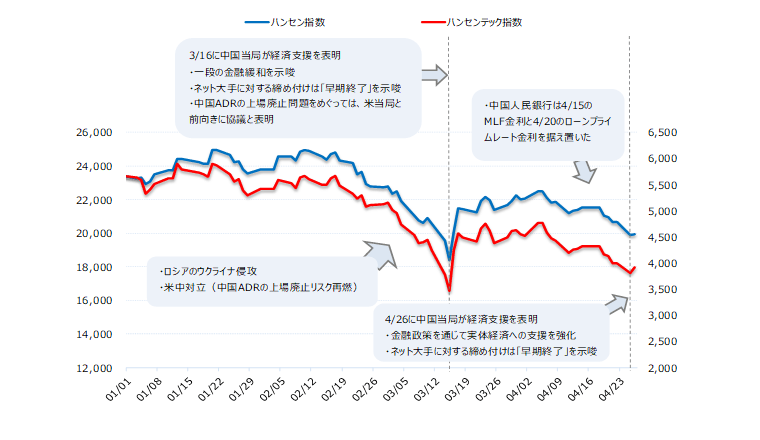
※Bloombergデータおよび各種報道をもとにSBI証券が作成
主要株価指数の4/26の反発と、中国当局が相場支援を表明した3/16の反発を比較してみると、4/26の上昇幅は3/16より小幅にとどまっています。主な要因として、以下3点が考えられます。
1)中国当局が4/26に示したのは「包括的な金融緩和」というより、的を絞った支援策を中心とする金融支援となっています。具体的には「新型コロナの流行によって大きな打撃を受ける産業や小規模企業を中心に、実体経済への穏健な金融政策の支援を強化する」ことです。
2)株式市場では的を絞った金融支援もさることながら、上海ロックダウンの早期解除がより経済にポジティブとみる向きが多くなっています。ウィズコロナの方が経済再開を促し、サプライチェーン問題の悪化を食い止められると期待されるからです。
3)1回目の支援表明後、政策の実行に至ってない部分も多いため、今後の具体的な政策発表とその実行を見極めたい投資家が多いようです。たとえば中国当局は4/26に新エネルギー車やグリーン家電の消費促進と、インフラ建設(空港などの輸送ハブ、エネルギーや水資源のプロジェクト)を強化する方針を示しました。それを受け、電気自動車(EV)関連銘柄は4/26に反発しましたが、4/27前場では利益確定売りが目立ちました。関連部門や地方政府による具体的な消費促進策の確認とその効果を見極めたいとする向きが多いようです。
総合的にみると、中国当局は今のところロックダウンを続きながら、的を絞った金融および経済支援で景気減速に対応しているようです。効果が確認されるまである程度時間がかかると想定されることに加え、「早期のロックダウン解除」に対する投資家の期待がより強い点を踏まえると、短期的に中国株が3/16以降のように急反発する可能性は高くないかもしれません。一方、ロックダウンが永遠に続く可能性も低いうえ、一連の金融や経済支援策(的を絞ったものであっても)が景気を下支えすると見込めるため、主要株価指数に対しては下値切り上げにつながる可能性がありそうです。
なお、人民元をめぐっては、一段の元安が進む可能性があります。過去の経験からすると、中国経済に下押し圧力がかかる時、中国人民銀行は元安を容認してきました。元安は輸出業者への圧力の緩和につながるため、一種の景気テコ入れ策にもなるからです。直近の実例として、2020年3月の新型コロナの感染拡大時や2018年の米中貿易摩擦時が挙げられます。
最後に、株式市場への影響を考えるうえで、過去の動きを確認してみたいと思います。2015年以降の人民元対ドルレートとMSCI中国株指数の動きを確認してみると(図表6)、必ずしも連動しているわけではありませんでした。ただし、元安局面を切り取ってみると、緩やかな元安が続いた場合は中国株にとってプラスといえそうです。一方、急激な元安が進んだ場合(例えば2018年)は株安が同時進行しました。中国人民銀行が4/25に元安阻止に動いたことからすると、中国当局は緩やかな元安を望んでいるようです。実際、中国人民銀行が4/25に外貨の預金準備率を引き下げた後、人民元の動きは落ち着きを取り戻しています。他方、足元で中国および世界経済をめぐる不透明感も強いことからすると、急激な元安が進んだ場合は警戒が必要かもしれません。
図表6 人民元対ドルレートとMSCI中国株指数の推移(2015年以降)
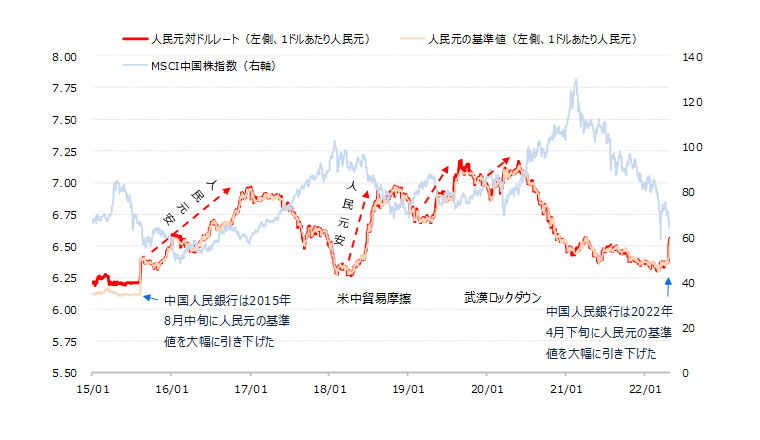
※Bloombergおよび各種資料をもとにSBI証券が作成
- ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。


 元安の背景
元安の背景
 中国当局の動きと株式市場への影響
中国当局の動きと株式市場への影響